循環はみんなを幸せにする
「好きなこと」で「社会を『もっと』よくする」仕組みづくり
アミタとハーチ、2社に共通する合言葉は「サーキュラー(循環)」。Webメディアでありながら、自治体事業支援や共創プロジェクト創出等へも事業を拡げ、循環型社会実現を独自の角度からズンズン推進するハーチはまさにサーキュラーの申し子!
しまうまフレンド四組目は、メディアの力で世界を幸せにする、ハーチ株式会社代表の加藤 佑さん。レッツ!しまうまトーク!
目次
※アミタは、7月4日(木)にハーチ株式会社 加藤様をお招きし、「サーキュラーデザイン」に関するセミナーを実施します。サーキュラーデザインの基礎知識から先進事例、消費者を巻き込んだ取り組み方法まで解説します。ご興味のある方はぜひセミナーホームページをご確認ください。
サーキュラーは突然に
突然の大雨、傘を忘れた末次は、カフェのような場所へ飛び込んで雨宿りをすることにした。
末次:あれ、ここってブックカフェ?本がたくさんある。私設図書館かな。
んん?本持って帰っていいって書いてある。どゆこと?
まぁいいか。面白そうな本がいっぱいあるな。どれどれ。
本を取ろうと伸ばした末次の指先が、同時に手を伸ばした隣の青年の指に触れた、その瞬間。ビビビッ!!!電気のようなショックが走る。
末次:アチッ!!
謎の青年:ツアッ!!
ーーーー衝撃を受けた2人は何かの運命を感じ、しばらく見つめ合う。。。ーーーー
末次:・・・サ、サーキュラー?(え、俺はいったい何を口走っているんだ?!)
謎の青年:エ、エコノミー?
末次:なに?!あ、あなたはいったい!?
謎の青年:私は、ハーチという会社の代表で加藤といいます。そういうあなたはいったい?
末次:なんと、ハーチの加藤さんでしたか!僕です、僕、今度対談させていただく末次です。これって運命だな!この場所ももしかして、ハーチさんと関係がある場所ですか?
加藤氏:末次さん!どおりで運命の電気が走るはずだ。はい、ここはハーチが運営する横浜の循環経済を促進するプラットフォーム「Circular Yokohama」の活動拠点なんです。この本は気に入ったら持って帰ってください。「値段がつかなくなってしまった本」を集めて、古本を循環させる「めぐる星天文庫」という取り組みなんですよ。
末次:それは素敵だ!ナイスサーキュラー!
今度ゆっくり循環についてのお話を聞かせてください!
 めぐる星天文庫
めぐる星天文庫
異業種へアーチ(橋)をかける企業の起源
末次:この間は、突然の運命の出会いをしてしまったわけですが、もともとハーチさんて、僕の中では謎が多くて興味深々だったんです。Webメディアなのにスタートアップの支援をしていたり、異業種の企業と協業で事業をされていたり、いったい何者なんだろうと。今日は、ハーチさんの経営ビジョンとか、どういった経緯で今の事業になったのかとか、お聞きしたいなと思います。そんなにパチッとおっしゃらなくても良いんですけど。
 加藤氏:パチッとは言い切れないかもしれませんが(笑)
加藤氏:パチッとは言い切れないかもしれませんが(笑)
僕は創業当初から、全員が、自分らしさや自分の得意なこと、好きなことを通じて、誰かの役に立っていると実感できることが一番の幸せなんじゃないかなと思っているんです。だから、それを誰もが実現できるような社会を作りたいという考えがベースとしてあります。
一人一人が本当に表現したいことができる社会を作るために、僕たちは何をすればよいのか。常に問いを立てつづけ、できることをやってみよう、という足跡が今の事業なんです。
今は循環型社会の実現にスタートアップが必要だと考え、スタートアップ創業のサポートもさせていただいていますが、2年後には状況も変わっているかもしれません。「今、より良い社会をつくるためには何が必要か」にフォーカスしていて、そこをずっと考えて悩みながらやっていく、そのプロセスを最後に楽しかったねって思えるようにしたい、というか。
末次:なるほど。ハーチという会社名、すごくかわいいなと僕初めに思ったんですけど。今伺った会社の理念と関係があるんでしょうか。
加藤氏:そうですね。ハーチという社名は、アルファベットで書くと「Harch」なんですが、人のココロ(Heart)とココロをつなぐ架け橋(Arch)のような存在になること、という想いが込められた造語です。事業としては、人の心を動かすメディアやコンテンツづくりを通じて、新たな出会いを生み出していくことを行っています。
末次:ハーチって造語だったんですね!僕の子どものころのアニメに「みつばちハッチ」ていうのがあって。てっきりそっちかと、いやまぁそれは置いといて(笑)
メディアにもいろいろあると思うんですが、加藤さんがぐっとサステナビリティの分野にフォーカスし始めたのには、なにかきっかけがあったんですか。
加藤氏:今のような事業のきっかけとなっているのは、大学生のときの出来事ですね。
当時、大学1年生で、浮かれていろいろおしゃれとかしてたんです(笑)ある日、一目惚れするような服を見つけ、ちょっと高かったんですけど、奮発して買ったんです。その後いろいろホームページとか調べたら、そのブランドが洋服のデザインとしてすごくかっこよく「戦争をやめよう」といったソーシャルなメッセージを伝えていたんです。ファッションをメディア化して社会的なメッセージを発信するという、こんな伝え方があるのかと思いました。自分も将来は社会問題をかっこよく伝えるようなことをやりたいな、と思ったのがきっかけですね。
末次:ファッションを見たときに、それをメディアと認識した点がユニーク!!目に見えるものから情報に視点を移すということですね。あ、でもそこはちょっと僕らも似た部分があるかなと思います。
例えば卵の殻。普通の人は、卵の殻ですと言ったら "ごみ"と認識するんですけど、僕らは卵の殻にはカルシウムがたくさん溜まっているので、乾燥させて粉々にしたら良質なカルシウム原料になるな、と認識するんですね。僕らの仕事は、情報をどういう風に切り取るかとか、情報の加工編集だと思ってるんですよ。
加藤氏:一見全然違う廃棄物と資源も、元素レベルで見れば同じだったと。まさにそれ。捉え方を変えるというのは、すごく大事だと思っています。例えば経済も、何かカタチがあって目に見えるものではなくて、ある種、集団的な幻想じゃないですか。社会もそうですよね。みんなでイマジネーションについて議論しているので、その頭の中のイマジネーションを変える、ものの見方を変えることがやはりすごく大事。
一人一人がメディア
 末次:アミタには、「What is Value?」 というコーポレートメッセージがあるんですよね。価値とは何かということを定義し直す。これはハーチさんにも通じると思うんです。何が本当の価値か。「資源」というのか「ごみ」というのかは、情報をどう見るかによって変わりますよね。おっしゃるように、想像力と洞察力で何でも変わるこの世界だと思います。
末次:アミタには、「What is Value?」 というコーポレートメッセージがあるんですよね。価値とは何かということを定義し直す。これはハーチさんにも通じると思うんです。何が本当の価値か。「資源」というのか「ごみ」というのかは、情報をどう見るかによって変わりますよね。おっしゃるように、想像力と洞察力で何でも変わるこの世界だと思います。
その情報を伝えるメディアの立ち位置については、なにか思われることはありますか。
加藤氏: ハーチは、自分たちが価値があると思っていることや、本当にやりたいことを表現する、表現企業を目指しているんですよ(笑)僕らはさっきお伝えしたみたいに、ものの見方を変えるのがミッションそのものとも言えますね。世界ともう一度出会い直すとか、地域と出会い直すとか、人と出会い直すとも言える。社会を良くするって言っちゃうと、今の社会がすごく悪いことになるし、そういう前提が必要になってしまう。ハーチに限らず、世の中の一人一人がメディアで、ファッションとか生き方を通じて、世の中に対して何かを表現しているのだから、それを邪魔するとか、良い悪いをジャッジすることはしたくないと思っています。それもあって「社会を『もっと』良くする」という表現をしています。今の社会も良いけど「もっと」良くできるよね、というスタンスで、見方を変える媒介者がメディアだと思っています。
例えば、人間はインプットしていない言葉は話せないわけですから、強い言葉を使う人がいるとしたら、たぶんそういう言葉を浴びているからアウトプットされているだけだと思うんです。だとしたら、自分たちが大量にポジティブなインプットをすれば、ポジティブなアウトプットが増えるんじゃないかとシンプルに思いますね。ものすごくシンプルなメディア機能を果たすことが、すごく大事だなと思っています。
末次:確かに、日々何をインプットしているかによって、人の発言や思考は左右されますよね。今、世界はこれだけ多極化してるし、ネガティブキャンペーン張りまくりで、人間の脳の問題かもしれませんけど、ネガティブなことにピントが合いやすくなっている。だからこそ、なるほど...メディアの役割とは、という部分に触れた気がします。
加藤氏:ちょっとでもポジティブな情報を増やすことでみんなが幸せになるんだったら良いなと。
あと、もう一つ大事にしていることとして、すでにある情報や取材で聞いた話だけではなく、ライターやエディター自身が自分で体験した話を発信する、ということがあります。自分で体験して感じた主観をたよりに発信する。そうすると、その時々の時代で誰がどう感じたかというスナップショットが撮れる。そのスナップショットが今のメディアの価値だなと思いますね。
 ハーチ主催のロンドン視察の様子
ハーチ主催のロンドン視察の様子
循環者になれ!
加藤氏:私もアミタさんにすごく興味深々で、アミタさんにとって循環って何なのかなとか、あとどうビジネスにしているのか、傍から見ているとよく分からないところもあって。
末次:ハーチさんがそれ言います?(笑)ご存じのとおり、私たちは『ひと・自然・もの・情報』のすべてがつながって循環(サーキュラー)する社会を目指しています。価値がないとされているものに価値を見出して、付加価値を利益にする。さらに、これまで世の中になかった循環の仕組みを構築することで、ビジネスの優位性と継続性をつくってきました。だから、情報の見方を変える、価値を定義し直すことがビジネスの起点になるんです。
加藤氏:確かにそうですね。みんなが価値がないと思っているものを循環利用できれば、仕入れが安くなりますし。アミタさんの事業の価値創出の源泉って、そういうところにあったんですか?
 末次:そうそうそう。創業は姫路のわずか数人の小さな会社から始まって、でも周りは大きくて強い企業ばっかりだし、当時リサイクルだなんだと言ったって聞く耳持ってくれないわけですよ。そこに価値があるのは分かってるけれども「それは何なんだ」「他のメーカーの製造工程から出た副産物です」って言った瞬間に「そんなごみをうちの商品の材料に使えるか!」と言われる。しかも、副産物なので安定供給が難しく、複数の工場から副産物を集めてきて、流通や保管や加工の仕組みを工夫し、量と品質を安定化させるオペレーションが必要になる。でもこれらの課題をクリアできれば、競合のいない新しいビジネスになる。普通、均質的で安定的な原料を大量に仕入れることが効率的な工業社会のセオリーですけど、その逆張りみたいなビジネスをずっとやってきたんですよね。
末次:そうそうそう。創業は姫路のわずか数人の小さな会社から始まって、でも周りは大きくて強い企業ばっかりだし、当時リサイクルだなんだと言ったって聞く耳持ってくれないわけですよ。そこに価値があるのは分かってるけれども「それは何なんだ」「他のメーカーの製造工程から出た副産物です」って言った瞬間に「そんなごみをうちの商品の材料に使えるか!」と言われる。しかも、副産物なので安定供給が難しく、複数の工場から副産物を集めてきて、流通や保管や加工の仕組みを工夫し、量と品質を安定化させるオペレーションが必要になる。でもこれらの課題をクリアできれば、競合のいない新しいビジネスになる。普通、均質的で安定的な原料を大量に仕入れることが効率的な工業社会のセオリーですけど、その逆張りみたいなビジネスをずっとやってきたんですよね。
加藤氏:なるほど。いやなんか、今初めて単純に「サーキュラー」と「ビジネス」がどうつながるのかちゃんと理解できた気がします(笑)循環っていうのは今のところアミタさんの真ん中にある概念なんですね。
末次:そうですね。循環って全然完璧じゃないし、作った瞬間から状況の変化によってほころび始めるんです。乱れを素早く感知し、それをどういう風に補正し安定化させ続けるか。そのためには、ものの循環と同時に、丁寧な関係性を紡ぐよう心がけることによって、情報共有や意思疎通をスムーズにしておき、速やかに課題の発見と対策ができるようにしておく。常に通用する最適解なんて無くて、どういう風に最適化していくか、という動的なプロセスが大事なんじゃないかなと思っています。
加藤氏:確かにものの循環だけではなく、関係性も循環していますよね。
末次:アミタの事業は、これまでどちらかというと、産業へのアプローチが多かったんですね。ただ、社会全体の循環を本気で考えると、企業の「作って・売って」だけではなく、暮らしにもフォーカスをあてて、企業と自治体が連携しながら、消費者が購入した製品が地域内で循環するような仕組みづくりとか、産業も暮らしも全体的に捉えて価値を作る必要があると思っています。
そこで、ここ数年注力しているのが「MEGURU STATION®」の展開です。ごみの回収という生活の一部をきっかけに、住民の方の生活習慣や行動も変容していきましょう、というコミュニティ機能をもった資源回収ステーションなんです。
今後はもっともっとパワーアップさせて、MEGURU STATION®を軸に、製品のトレーサビリティやCO2情報、需要予測など、見えない価値を可視化するように展開していきたいと思っています。こういった情報に広くアクセスできるようにすることで、きっと生活者が「好き」という自己表現をしやすくなるようになるのではと思っています。
 福岡県大刀洗町のMEGURU STATION®
福岡県大刀洗町のMEGURU STATION®
加藤氏:それ、すごく理にかなっているなと思います。以前欧州に行って感じたのですが、日本は欧州ほどエシカル消費が盛んではないものの、日本人特有の気質からか、ものを捨てるときのモラルは他国に比べてとても高いと感じるんです。だからこの特性を循環経済のドライバーとして活用できないかな、と私も思ったことがありました。
これからは、ものの手放し方も自己表現の一つになるし、そのときに「循環」を選んでほしい。「消費者」ではなく「循環者」になっていこうと。どんな風にものを手放すか。手放し方でものの価値は変わるんですよね。それに、住民の方が「循環者」として役割を担えば担うほど、地域全体に還元されていって、パブリック・ウェルビーイングが高まっていく。アミタさんのMEGURU STATION®では、回収したプラスチックでベンチを作って住民の方に還元されていましたよね。
末次:おお!よくご存じで!
加藤氏:そういう風に、個人が分別や回収に頑張って協力したことが、目に見える形で、しかもパブリックに現れる。これは幸福度も高まるし、納得してみんなが頑張れるシステムで、もっと広がってほしいですね。
末次:ありがとうございます!その加藤さんの記事読みましたよ!
僕らは『消費者』じゃなくて『価値の生産者』という言い方をするんですけど。
例えば、これからは様々な原料の調達リスクが問題になりますよね。そうなると、必然的に再生資源が求められて、これまでいらないと捨てていたものも資源になっていく。加藤さんがおっしゃるように、どういう風に資源としてパス出していくかという「手放し方」が価値の起点となっていく。それはもう暮らしの在り方そのものですよね。人間の好き嫌いも、生活習慣とか暮らしの中で生まれてくるものがあると思うんですよ。今の時代、いろいろなメディアから、こういうのが良いとか、かっこ良いとか、ある意味思い込まされてるとこもあるじゃないですか。自分が良いって言っているのか、言わされているのか、もはや分からなくなっている。その時に、自分の足で立ちながら感じられるのは、やっぱり日々の暮らしの中で生まれてくるものじゃないかなと思うんです。
 加藤氏:いやもう本当にそう思いますね。今、横浜では「横浜リユースびんプロジェクト」というのが進んでいて、市内でのリユースびんの循環システムを構築しようとしています。びんが再利用されるのはもちろん、中身も地元の果物を使ったオリジナル、その飲料を使用するのも地元の飲食店、びんは地域を循環し続けて。僕たちの横浜にある拠点でも取り扱いを始めているのですが、地域の方がびんを返しに来てくださるのは嬉しいですね。
加藤氏:いやもう本当にそう思いますね。今、横浜では「横浜リユースびんプロジェクト」というのが進んでいて、市内でのリユースびんの循環システムを構築しようとしています。びんが再利用されるのはもちろん、中身も地元の果物を使ったオリジナル、その飲料を使用するのも地元の飲食店、びんは地域を循環し続けて。僕たちの横浜にある拠点でも取り扱いを始めているのですが、地域の方がびんを返しに来てくださるのは嬉しいですね。
末次:楽しそうなプロジェクトですね!今度、お店にボトルキープしにいきます。あ、でもびんに名前書いたら怒られるか(笑)
人生の割り算
加藤氏:突然ですが、末次さん算数は得意ですか?
末次:え~、まぁ、一応経営者なので苦手だとは言えないですね(笑)
加藤氏:算数の問題ではないんですが、利益を分け合うのって結構みんな得意じゃないですか。でも、痛みを分け合うのはすごく苦手ですよね。僕は両方うまくシェアできるようなモデルがあると良いなと思うんです。
末次:確かに、利益を分け合うことと痛みを分け合うことは、人によって得意不得意がありますね。でも、お互いに助け合える仲間がいると、痛みも少しは和らぎます。

加藤氏:輪廻転生(次の命がある)と仏教ではいうけれど、やっぱり人生の時間は無限じゃなくて有限ですよね。その中で何を詰め込むか。それは経済であれウェルビーイングであれ、必ずその割り算になっちゃうと思うんです。分母が時間だとして、分子がお金かもしれないし、幸せかもしれない。そうなると、どうしても「効率」みたいな考えからは逃れられなくて、分け合うというと聞こえはいいけど、自分が大事にしたい分子につながらない部分を外部化しているだけとも言えなくもないと考えると、難しいですね。
末次:確かに難しいですが、これも見方一つかなと思いますね。僕らよく、何のために働くかという話をするんですが、昔は食べるために働いてきたんだと思うんです。
今の時代、賃金労働もバカバカしくなって、YouTubeでバズれば一生食べていけるし、資産運用でファイヤーする人もいたり。じゃあ何のために働くんだろうと考えると、人はやっぱり関係性のために働くんじゃないかって。
さっきの分子が何かという話なんですけど、有限な時間で分母は決めましょうとなった時、僕はその分子は関係性だったら良いんじゃないかなと思いました。関係性は別に広げようと思ったら無限に広がるし、人との出会いがある。ある意味イマジネーションでも広がっていきますよね。今日加藤さんとお話しすると、また一つ僕にとっては新たな価値が分子に乗っかってくるわけですよ。豊かな時間と関係性の蓄積が分子になる。
加藤氏:僕もそう思います。
末次:僕も全然悩みながらなんですけど、効率を基準に不必要な部分を切り捨てて自分たちが儲かるように仕立てるのではなくて、関係性の中でどう価値を生み出し、シェアするかってことを考えないといけないと思うんですよね。経営として必要な資産をどういう風に重なり合わせながら、ある意味軽くしていくか、その中で利益をつくるやり方、内部化・外部化のさせ方があるんじゃないかと。
さっきの手放し方や痛みの話にもつながりますが、循環することは、その非効率さや痛みもシェアして、全体最適化できないと、回り続けられないんですよね。その過程の中でこそ意味のある関係性や情報資源が増えていくんだと思います。
加藤氏:そこは問われてるなと本当に思っています。ベトナムの禅僧のティク・ナット・ハンさんの言葉で「インタービーイング」という言葉があって、「宇宙にあるすべてのものは相互につながりあって存在している」という意味なんですけど、関係性って本当インタービーイングだなって。関係性の中で現れてくる価値があって、ウェルビーイングもそうだと思うんですよね。還元主義的に個人のウェルビーイングを追求しても、その足し算は地域のウェルビーイングにはならないと思うんです。個人のウェルビーイング同士にも、対立や衝突はあるし、地域のウェルビーイングにもある。だから、最終的には関係性。どうやって関係性の中でよりよくなれるのかという、インターウェルビーイングみたいな感覚が重要かなと。
末次:そうそうそう!アグリーですね!
加藤氏:もっとみんなが共有できるようになると巡る気はしています。
末次:僕らが事業家として、1社1社の利益はあるけれども、結局「We」という主語でどこまで認識できるかという。
加藤氏:いやー、もう本当にそう思いますね。アグリーです。
末次:さっきの加藤さんの「一人一人がメディア」という言葉、それってすごく良いメッセージだなと思うんです。結局、みんなそれぞれだし、さっきも仰っていた主観みたいなことがあって初めてメディア化すると思うので。
加藤氏:そうですね確かに。
末次:僕らも、熊野から「過ごすんじゃなくて生きなさい」と言われるんですよね。有限な時間の中でどう生きるのか。なんとなく過ごすのではなくて、生きてるんだっていうことをどう表現するか。「一人一人がメディア」というの、すごく根源的で良いなと思いましたね。
エコシステム経営
加藤氏:経営者になると苦手なこともやっていかないといけない場面もあるじゃないですか。悩むことも多いんですよね。末次塾とかあれば入りたいぐらいなんですけど(笑)
末次:入塾します?
加藤氏:しますします(笑)末次さんは、どちらをとっても五分五分と言える決断案件のとき、どうされていますか?
 末次:ひとつは、決断は時間軸で、と思っています。判断は空間軸というか、今の最適解でやるので、ある意味誰にでも見えますけど、今の判断としては非合理だとしても、将来どうなるかを見据えた決断は経営にしかできないですよね。
末次:ひとつは、決断は時間軸で、と思っています。判断は空間軸というか、今の最適解でやるので、ある意味誰にでも見えますけど、今の判断としては非合理だとしても、将来どうなるかを見据えた決断は経営にしかできないですよね。
もうひとつは、失敗したとしても学びやノウハウという資産として溜まって次につながるかと考えた時に、やるべきだったらやりますね。方法論のトライアンドエラーは何回やっても良いんですけど、目的がぶれるトライアンドエラーは経営資源を浪費するだけになります。目的に照らして、うまくいくかどうかじゃなくて、それによってどういう資本や資産がたまっていくのか。
基本的には関係性という資産が増幅するのであればやって良いんじゃないかって思います。例えば、ビジネスとしてはあまりうまくいかなかったけど、そこで500人のネットワークができた。それを資産にしながら新しいビジネスができる。あるいは、これが取材先になるかもしれないし、ライターさんになってくれるかもしれない。次にどういう風につながるか。そういう線が見えるかどうかですね。
加藤氏:なるほど、塾長!関係性の資産ですね!
末次:そうそう。熊野がとある経営者に対して「いろいろな人と弱く繋がっておきなさい」とアドバイスをしたことがあったそうなんです。その後、経営に行き詰まった時、その弱~い繋がりで助けられたことがあったらしいんです。ようは、何を仕入れとして、何を資産として認識するのか、何をシェアできるのか、その解像度を上げて言語化して、さらにそれをどう価値創出のメカニズムにしていくのか、が経営の腕の見せどころなんでしょうね。
加藤氏:すごい分かります。
末次:アミタは今、いろいろな会社と合弁会社を作ったりしながら、エコシステム型の経営や組織づくりを目指しているんですが、どういう風に組織のデザインをしていくかというのは、過去のやり方では難しい時代になっていると痛感しますね。
加藤氏:確かに確かに!私たちはビジネスモデルを考えるのは苦手で、正直教えて欲しいんですけど(笑)いろいろな方とお話をしている中で、サーキュラーエコノミーのエコシステムを作ることがメディアとして果たす役割なのかなって思いましたね。
例えば、ただコラボレーションやりましょう、集まりましょうと言っても誰も集まらないじゃないですか。でも「スタートアップの創業支援」といったテーマがあると、いろいろな人が集まりやすいんです。企業の人も自治体の人もスタートアップの人もメンターの人も。そこからまたいろいろな繋がりをもって関係性も育まれて。そういうのが、僕たちがエコシステムに貢献できる形なのかなと思っていますね。
 サーキュラーエコノミー特化型スタートアップ創業支援プログラムにおける
サーキュラーエコノミー特化型スタートアップ創業支援プログラムにおける
パネルディスカッションの様子
末次:コンサルの支援なんかをしていると「成功するほど失敗する」ってよく言うんですよね。やっぱり成功した会社さんほどその成功モデルから抜け出すのは難しいし、イノベーションって言わば辺境からしか生まれないと思うんです。ひょっとするとスタートアップに関わっていたいっていうのは、自社の中でのイノベーションが難しくなっているので、その機能を外出ししたいということかもしれませんね。
「競争」はやめて「共創」する
末次:イノベーションといえば、2024年の4月にアミタが発起でESA(イーサ)という一般社団法人を設立したんですよ。社会全体の持続性を高めるイノベーションを起こそう!と。社会全体となると、もう―企業でやるには難しいですし。
加藤氏:イーサ?し~んぱ~いなイサ~!てライオン被って言うやつですか?
末次:違います(笑)
ESAは、一般社団法人エコシステム社会機構(Ecosystem Society Agency)の略称で、『ライオン・キング』のモノマネをする某お笑い芸人でも沖縄の方言でもありません。(笑)
コンセプトは、制約条件下でも心豊かな(ウェルビーイング)生活を送ることができる持続可能な社会を実現することで、キーワードは「循環」と「共生」です。人口減少・少子高齢化や新しい政策課題に直面する地方自治体と、新たなビジネスモデルの創出を目指す企業が、統合的思考に立ってイノベーションを起こし、社会的価値を創出するプラットフォームとなることを目指しています。循環は作った瞬間からほころび始めるし完璧ではない、という話をしましたよね。完璧じゃなくて良いし、どんどん既存のものは壊して形を変えてシェアをして循環させる。詳しくはリリースがあるんで見てください(笑)
先ほどの、イノベーション機能の外出しの話じゃないんですけど、今の社会ってよくできたメインシステムがあるんです。でも実際には、サブシステムがメインシステムに影響を与えていて、サブがないとメインが動かない、なんてこともありますよね。循環して持続可能な社会をつくるには、健全なサブシステムみたいなものを作っていく必要があるんだろうなという構想はあったんですが、今回それがやっと形になった感じです。
加藤氏:エコシステムって、まさに今のサブシステムですよね。本質的に完璧な設計は難しいと思うので、たまにちょっと栄養素を投入して、それに刺激されて新しいものが生まれていく、みたいなことを常にやり続けたいなと私も思っています。
末次:僕らも思うんですけど、もうCircular Economy(循環経済)ではなくて、Circular Society(社会)だなって。どういう風に包摂的な社会を作っていくのかという。企業だけ頑張ってもあまり意味なくて、人材もノウハウもハードもソフトも。全体最適で考えると、一企業としての資産は別にそこまで増やさなくても良くて、むしろいろいろな会社さんの資産を関係性の中で互いに使用しあって、共創的に価値を生み出していくことがこれからは必要だなって思いますね。
 加藤氏:共創といえば、大阪の梅田に9月に開設する「PLAT UMEKITA(ぷらっとうめきた)」にハーチも参画させていただくことになりまして。大都会のど真ん中に設置する大屋根施設で、オープンスペースのいろいろな人が集う公園という感じなんですけど。コンセプトとしては、生活者と企業をつなぐ体験型共創プラットフォームなんですが、官・民・学協働で、エシカル、サステナブル、ウェルビーイングなんかの新しい時代の価値観を楽しい体験に変換して提供する施設になる予定です。ハーチは常設展示や習慣的ワークプログラムの企画制作を担当するのですが、詳しくはリリースがありますんで見てください!(笑)
加藤氏:共創といえば、大阪の梅田に9月に開設する「PLAT UMEKITA(ぷらっとうめきた)」にハーチも参画させていただくことになりまして。大都会のど真ん中に設置する大屋根施設で、オープンスペースのいろいろな人が集う公園という感じなんですけど。コンセプトとしては、生活者と企業をつなぐ体験型共創プラットフォームなんですが、官・民・学協働で、エシカル、サステナブル、ウェルビーイングなんかの新しい時代の価値観を楽しい体験に変換して提供する施設になる予定です。ハーチは常設展示や習慣的ワークプログラムの企画制作を担当するのですが、詳しくはリリースがありますんで見てください!(笑)
末次:なんですか!そのワクワクしかない施設は!!絶対行きます!いや~しかし、時代は「共創」ですよね。「競争」する時代はもう終わったっていうか。
僕、今大発見しちゃったんですけど、アミタ+ハーチで"アーチ"ですよね!!!
もうこれは、必然というか神様のいたずらというか。バチバチに出会った運命感じちゃってます。
社会の様々なものをサーキュラーさせるため、これからぜひいろいろなことに一緒にアーチ(橋)を架けて循環させていきましょう!
サーーキュラーーーー!!!!
加藤氏:ソサエティーーーー!!!!塾長!やってやりますよ!
(僕こういうキャラじゃないんだけどな。。。笑)
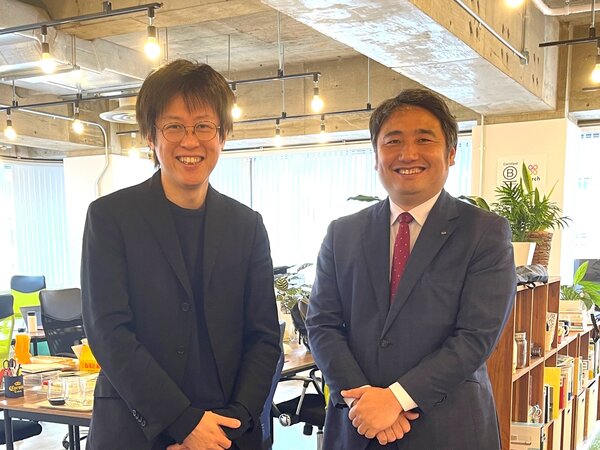
対談者 | 加藤 佑 氏(ハーチ株式会社代表取締役)
1985年神奈川県生まれ。株式会社リクルートエージェントなどを経て、2015年にハーチ株式会社を創業。社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」、循環経済専門メディア「Circular Economy Hub」などのデジタルメディアを運営するほか、横浜の循環都市移行プラットフォーム「Circular Yokohama」、東京都における「CIRCULAR STARTUP TOKYO」など、企業・自治体・教育機関との連携により循環経済推進に従事。英国ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所Sustainable marketing, media and creative修了。東京大学教育学部卒。
関連情報
アミタは、7月4日(木)にハーチ株式会社 加藤様をお招きし、「サーキュラーデザイン」に関するセミナーを実施します。サーキュラーデザインの基礎知識から先進事例、消費者を巻き込んだ取り組み方法まで解説します。ご興味のある方はぜひセミナーホームページをご確認ください。



